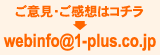ch04.カルチャー: 2010年3月アーカイブ
ch04.カルチャー : 詩集 |
||||
最近はどういうわけか、しばし忘れていた本に手をのばすことが多くなった。
たまたま、現在、長野県安曇野にある虹の村診療所・意識教育研究所の所長である小林正信先生のお話しの中で、先生が三好達治の一篇の詩をよまれた。「わが名をよびてたまはれ」という詩であった。二回ほど繰り返しよまれた。うつ、不登校、ひきこもりなど心に問題をかかえる子どもたちと日々会話をかわす小林先生の優しい気持ちが感じられる。よまれている時に、こんな季節の空気が妙に懐かしくも思えた。
春といえば、新しい教科書を手にワクワクしながらそれぞれの教科の教科書の一ページを開いたものだ。国語などは必ず詩があった。当時はそれほど気にもならず過ぎていた時間が今になってみるとこんなにも懐かしいものかと思える。
帰宅してから、書棚の上の方をぐるぐると見回してみた。「あった・・・」。三好達治の詩集。詩などゆっくりよんでみようなどと言う気持ちは久しぶりの事だ。打ち合わせ、料金交渉、締め切り、受注だ発注だと気持ちはいつもギリギリとしている。ささくれる時だってある。そんな慌しいだけの日々の中で、ソーダ水のように何かが弾け飛ぶ。ひとつひとつの詩人の言葉を目でおうだけでなく、ちょっと声をだしてよんでみた。ああ!一篇の詩。
わが名をよびてたまはれ
いとけなき日のよび名もてわが名をよびてたまはれ
あはれいまひとたびわがいとけなき日の名をよびてたまはれ
風のふく日のとほくよりわが名をよびてたまはれ
座のかたへに茶の花のさきのこる日の
ちらちらと雪ふる日のとほくよりわが名をよびてたまはれ
よびてたまはれ
わが名をよびてたまはれ
(三好達治)
ch04.カルチャー : 春の愉しみ |
||||

型絵染版画作家のさかもとふささんとは本当に長いお付き合いになる。日本や外国の風景や祭り、動植物など様々な題材を作品にしてこられた。型絵染版画は日本の伝統工芸の着物の染色技法を使ったものだという。最初にさかもとふささんの作品を拝見した時は、その何ともいえない風合いにドキッとしたものだった。2003年からはオーストリアのウィーンを中心にスロバキア、チェコ、ウクライナなどで展覧会を開催してこられた。外国でも好評なその魅力が何なのか?作品を間近に見ると分る筈だ。今回はハイドン教会などオーストリアの風景を中心に、動物、植物の新作を含む約25点を展示する展示会が企画された。花見の季節だがまだまだ吹く風が冷たい。でも、もう直ぐ、美しい花と素適な作品に出会えそうだ。
さかもと ふさ 型絵染版画展
会期:2010年4月2日(金)~13日(火)
時間:11:00-19:00(水曜休廊)
会場:国立・ギャラリーカフェ亀福
ギャラリー亀福ホームページ
ch04.カルチャー : 庭師の仕事 |
||||
米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」が「2009年日本庭園ランキング」を発表し、初回の2003年から7年連続で「庭園日本一」に選ばれた足立美術館の庭園。「成功の要因は、美術館のスタッフ一人ひとりが毎日参加する、徹底した庭の手入れと維持管理によるところが大きい」と評価されている。
創設者の足立全康氏は92歳で亡くなるまで、自分の目と足で全国から植栽の松や石を蒐集し、庭造りに情熱を傾けたという。枯山水庭をはじめ、50,000坪にもおよぶ6つの庭園には四季折々の表情を醸し出している。
勿論、日本庭園にはそれぞれの美しさがあり、それこそ好みというのもある。私自身、大好きな日本庭園も沢山ある。庭園というものでなくても、例えば主を失って、それでも季節ごとに木々の芽の息吹を感じる、そんな庭も好きである。
この足立美術館の庭園は何とも不思議な感覚に捉われる・・・。日本人そして外国人の美意識や文化というものについて考えさせられる。冷静に冷静にそしてあつい気持ちで鑑賞しながら、自然と人工との見事な調和を感じる庭園なのかも知れない。
さて、この足立美術館の庭園部には、現在7名の庭師がいるそうである。日々休むことなく庭園の手入れを行い、また木々の手入れの合間をぬって焼いているものに竹炭スプーンがある。これまたひとつひとつ丁寧に作っているという。スプーンの他に炭のオブジェもすべて庭師の手によるものらしい。
※この足立美術館の創設者・足立全康の自叙伝『庭園日本一 足立美術館をつくった男』が、米国ストーン・ブリッジ・プレス社から英語に翻訳され出版される。(価格は2,700円(US$29.95)米国での発売日予定は2010年4月15日。
書籍名は『My Life in Japanese Art and Gardens- From Entrepreneur to Connoisseur』