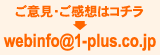ch04.カルチャー: 2012年4月アーカイブ
ch04.カルチャー : むかっ腹がたっても・・・ |
||||
少し時間が経つと不思議なもので、その時、むかっ腹がたったとしてもその怒りがぼんやりと消えていくものだ。数日前にもらったメールで腹立たしい気持ちが暫くおさまらなかった。別段、自分のことをとやかく言われたとかそういう類ではない。周囲の関係者、その好意に対して、あまりにも想像力がないというか、洞察力がないというか・・・。あまりにもつっけんどんというか切り口上というか。その言い方、いや書き方に一瞬腹が立った。決してその方は決して悪人ではないのたが彼女の性格がうまく文章に反映しないというものなのだろう。
小学生の時の担任がいつもいつも「文は人なり」と仰っていたが、いつも念頭においている。相手そしてその周囲の人々に対して気遣う、そんな気持ちが少しでもあれば・・・。
よく考えると文章力とはやはり鍛錬そして鍛錬であるところもある。友達や子どもや連れ合いなどに対するメールとビジネスメールでは全く異なる。メールとは、ビジネスシーンで相手を怒らせてそれで終わり!ということだってある。就活だって人事担当者はしっかりとこのへんを見るのだ。怒りもおさまれば向かっ腹メールを、「相手を慮った文章」に修正していく、そんな訓練も必要かもしれないな。常に謙虚に生きよう。
ch04.カルチャー : 旅に出たくなる本屋さん |
||||
ch04.カルチャー : 「坊主バー」で琵琶演奏を愉しむ |
||||
 昨夜は四ツ谷荒木町の「坊主バー」で琵琶奏者・大峯香風さんの琵琶演奏を聴く。「坊主バー」のマスターの藤岡さんは"美坊主"で有名な方であり、且つ大峯さんは今、テレビやラジオでも大活躍の女性琵琶奏者である。筑前琵琶に薩摩琵琶。琵琶の音は悠久の時へと誘ってくれる。マスター藤岡さんは大峯さんのお弟子さんでもあり、彼の演奏も楽しむ。そして琵琶とピアノとの共演という不思議な世界も体験。そして「法話」でしっかりと人生についても考えてみる。
坊主バーはこちら
昨夜は四ツ谷荒木町の「坊主バー」で琵琶奏者・大峯香風さんの琵琶演奏を聴く。「坊主バー」のマスターの藤岡さんは"美坊主"で有名な方であり、且つ大峯さんは今、テレビやラジオでも大活躍の女性琵琶奏者である。筑前琵琶に薩摩琵琶。琵琶の音は悠久の時へと誘ってくれる。マスター藤岡さんは大峯さんのお弟子さんでもあり、彼の演奏も楽しむ。そして琵琶とピアノとの共演という不思議な世界も体験。そして「法話」でしっかりと人生についても考えてみる。
坊主バーはこちら
ch04.カルチャー : 脳の世界 |
||||
昔、 虫ばかり追いかけていた子どもであったが、ある瞬間に興味が湧いた"脳"の世界。いつだったか覚えていないが、大学時代も別段、専門のカリキュラムではないものの、何故か生理学の授業にせっせと出席してレポートもよく書いた。しかし、"脳"の話は、物覚えが悪くなっている今は若い頃は感じなかったが結構深刻ではある・・・ああ・・・
第53回日本神経学会学術大会市民公開講座『高齢期を豊かに生きる~脳の老化と認知症の克服~』(主催:日本神経学会、共催:文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」)を開催されるのでご紹介します。認知症の各疾患研究を専門とする講演者たちが一般の方にも分かりやすく解説してくれる。脳の老化や認知症について興味のある方は是非、ご参加を。
【日時】2012年5月26日(土)13:00~16:00
【会場】東京医科歯科大学M&Dタワー2階 鈴木章夫記念講堂(東京都文京区湯島1-5-45)
【参加費】無料
【定員】500人
【講演プログラム】
総合司会:桜井洋子(NHKアナウンサー)
1.「認知症とは? -とても大切な脳のお話-」
水澤英洋(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科)
2.「レビー小体型認知症を正しく理解する」
伊東大介 (慶應義塾大学医学部神経内科)
3.「前頭側頭葉変性症の臨床像と病態」
祖父江 元 (名古屋大学大学院医学系研究科)
4.「脳卒中、 認知症を予防する生活習慣」
冨本秀和(三重大学大学院医学研究科)
5.「アルツハイマー病の根本治療をめざして」
岩坪 威(東京大学大学院医学系研究科)
文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」の事業紹介および研究成果についてのパネル展示もある。。
※展示は12:00 ~17:00。
脳プロウェブサイト
ch04.カルチャー : 言葉を紡ぐ |
||||
君島芝田先生がメールで俳句のレッスンを始められた。「ハンドルネームを」と言われた時、Eモニターなどいつも「いいちこ」と名乗っているので今回は「こいち」という名前にしてみた。
日々、本当に胃が痛くなるほどの編集関連の締切をはじめ、最近では地震関連の仕事の受注も増大している。しかし、プロであればどんなことでも丁寧に対応してこなさなくてはならない。「吉田事務所」は小さな個人事務所と言っても一応会社を経営していると諸々のことが日々山積みである。たんたんとこなしていくことが一番であるのだが。
そんな日々の一瞬、芝田先生からの"今月のお題"と宿題がくると、何か不思議な空気感に包まれる。今月は「「花」「蝶」」「春風」であった。いつかは水彩画でも描いてみたい・・・と思っているが、俳句はまさに言葉の水彩画を描く、そんな空気感である。「言葉」を扱うが頭の中に描く光景や香り、それらは私の場合「絵画」に近い。
作句にはそれほど時間はかからない。取材途中の電車の中とか、取材の合間のほっと一息のコーヒーを飲みながら、手帳にメモする。本当に殴り書きのメモ程度である。しかし、言葉の数々を只管、紡いでいく。すると、その光景はいつのまにか、頭の中で動きだし、数々の息遣いがきこえ、そして風が吹いたり、甘い香りがしたりするのだ。
まさに、現在の私にとっては、日常の中の"非日常"である。
ch04.カルチャー : 時代の息遣いが聞こえる |
||||
夢とは見るものではなく掴むとか叶えるとかいうが・・・「としまの記憶」をつなぐ会がもうすぐNPOとしてスタート。少し前から取材中にいろいろ考えてというより妄想に近いが、あまりに鮮烈なお話を聞く度に、芝居にしたら面白いだろうなあと描いていた。何となく、ぼーっとしたイメージのようなものは出来上がっていた。しかし、私は演劇は好きでも仕事としてプロではない。だから演劇好きが描く、単なるイメージである。
戦前、戦中、そして戦後の復興。様々な街が時代の風に吹かれて姿を変えていく。人々との出会いと別れ。そして巡り会い。そんな話を聞けば聞くほどに息遣いが聞こえてきたのだ。
「としまの記憶」をつなぐ会のメンバー、劇団ムジカフォンテの知久晴美さんといろいろ話しているうちに何やら楽しく夢が具体化しそうな気配。実は、私はこの"気配"という言葉が大好きなのだ。今、確かにその気配を感じ取っている。
ch04.カルチャー : 定年塾とは? |
||||
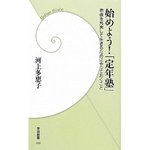 サンケイリビング新聞社勤務時代に一緒に仕事をした河上多恵子さんが「久しぶりに新刊を出版した」というメールを下さった。タイトルは『始めよう!「定年塾」~ 老後を充実して生きるためにやっておくこと』学研新書から840円。
なんでも50代以上の男性向けに書いたもので定年後を上機嫌に暮らすための方法をQ&Aとショートストーリーとデータでまとめたそうである。
ざっと内容をご紹介すると・・・・
サンケイリビング新聞社勤務時代に一緒に仕事をした河上多恵子さんが「久しぶりに新刊を出版した」というメールを下さった。タイトルは『始めよう!「定年塾」~ 老後を充実して生きるためにやっておくこと』学研新書から840円。
なんでも50代以上の男性向けに書いたもので定年後を上機嫌に暮らすための方法をQ&Aとショートストーリーとデータでまとめたそうである。
ざっと内容をご紹介すると・・・・
定年後を心豊かに暮らすために必要な能力を「定年力」とし、五つのフィールドで構成しています。
・「つながり力」 趣味、地域での暮らし方や友人の問題、
・「経済力」 仕事や年金、家計の問題、
・「健康力」 自分自身や家族の健康問題、
・「始末力」 相続や身辺整理の問題、
・「夫婦力」 夫婦の関係や子供の自立の問題
河上さん自身のメッセージは以下。たくさんたくさん類書を読まれて、そこで冷静に分析をされたのだなと思った。やはり河上さんは"実力者"だなと思った。
「従来の"定年もの"の書物は男性側からの心構えを説くもの、女性側からの要望を声高に言うもの、
定年後の暮らし方のルポ、年金等のガイド集が主だった。今ひとつ当事者の心理に響くものではないように思われます。本書では、気持ちのひだに分け入るような具体的項目を挙げて、楽しくも厳しく現状の確認を促します。そして、さまざまな物語を通じて、解決策をアドバイス、人生後半戦を生きていくためのエールとしています。仕事を続けてきた女性にもぜひ読んでいただきたいと思います。」
アマゾンからの購入はこちら
サンケイ時代は『リビング生活研究所』で一緒に主任研究員をしていた。特に女性マーケットの分析をしていた。レポートが発行されるやいなや、よくテレビ情報番組の制作会社からバイク便がやってきたものだ。そして翌日の番組で「最近の女性たちの・・・」と情報が流れたものだ。
思い出せば、アンケートの回答を分析する時に、当時「秀吉」とかいうソフトを使っていた。その次が「太閤」。なんとも面白いネーミングに、ふふふと笑ったものだ。今では何もかもが懐かしい。そして退職後も、それぞれがいろいろな得意な分野で活躍している。嬉しいかぎり!