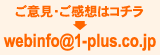ch04.カルチャー: 2011年7月アーカイブ
ch04.カルチャー : 空海 |
||||
この夏、もし一時間でもフリーになれる時間があれば・・・あれこれ考えたり言わずに是非!「空海と密教美術展」へどうぞ。
9月25日(日)まで。会場は東京国立博物館 平成館 (上野公園)です。何せ、密教美術1200年の原点、その最高峰が大集結です。展示作品の98.9%が国宝・重要文化財です。且つ、 全長約12mの「聾瞽指帰(ろうこしいき)」をはじめ、現存する空海直筆の書が展示されています。
気が付いたら私は2時間も会場にいました・・・・本当に圧倒される素晴らしさです。
ch04.カルチャー : パワー全開♪ |
||||
 朝から、 青島広志先生が指導する「少年少女音楽教室発表会」の取材に。いやあ、あんなに忙しい青島先生は相変わらずのパワー全開。子どもたちも弾けていた!いいね!本当に!しかし、青島先生の、あの漲るエネルギイはどこから生まれてくるのだろう?「右と左の眉の描き方が違うわよ!」と音楽ばかりでなく絵心もある青島先生は手厳しい・・・。いやはや。大慌てで鏡に向かった朝がもうバレバレである・・・トホホ。
青島広志先生のホームページはこちらです
さて、夏休みにふさわしいイベント紹介。8月20日(土)21日(日)に渋谷のシーシーレモンホールで「ブルー・アイランド氏のおしゃべりコンサートin渋谷『ファウスト君がんばってね!』」がある。シーシーレモンって何?という方。あの渋谷公会堂である!ああ~なんか懐かしい。それにブルー・アイランド氏つて青島先生?夏休みのひと時、青島先生の軽妙洒脱なおはなしも聞いてみるとパワー全開♪
詳細はこちらから♪
朝から、 青島広志先生が指導する「少年少女音楽教室発表会」の取材に。いやあ、あんなに忙しい青島先生は相変わらずのパワー全開。子どもたちも弾けていた!いいね!本当に!しかし、青島先生の、あの漲るエネルギイはどこから生まれてくるのだろう?「右と左の眉の描き方が違うわよ!」と音楽ばかりでなく絵心もある青島先生は手厳しい・・・。いやはや。大慌てで鏡に向かった朝がもうバレバレである・・・トホホ。
青島広志先生のホームページはこちらです
さて、夏休みにふさわしいイベント紹介。8月20日(土)21日(日)に渋谷のシーシーレモンホールで「ブルー・アイランド氏のおしゃべりコンサートin渋谷『ファウスト君がんばってね!』」がある。シーシーレモンって何?という方。あの渋谷公会堂である!ああ~なんか懐かしい。それにブルー・アイランド氏つて青島先生?夏休みのひと時、青島先生の軽妙洒脱なおはなしも聞いてみるとパワー全開♪
詳細はこちらから♪
ch04.カルチャー : 名優の死 |
||||
時として"毒"が忘れられないものだ。そんな毒を俳優の原田芳雄さんはもっていたと思う。しかし享年71 歳とは・・・若すぎるだろう。
かなり昔だが、作品名は覚えていないが、あの毒の魅力を持つ俳優としていつも頭の中にあった存在であった。いろいろなエピソードをきけば、やはりとことん優しい男だったのだと思う。
あの野太い声を失っても完成披露試写会の舞台にあがった。「もう俺には時間がないんだ」と監督に言ったそうだ。ふつうの人間ならとても言えない言葉だ。ふつうだったらただただ生き延びたいとパニックになるだけだ。胸がつまる。あの痩せた名優の姿は"毒"がどこにいったのか?と思えるほどだった。
原田芳雄最後の作品「大鹿村騒動記」を観る。真剣に見る。一人の名優がずっとあたためていたというテーマが何か、真剣に見る。
ch04.カルチャー : 俳句 |
||||
あの日。 雨が激しく降りしきる中を取材した日。
傘など役に立たぬほど強い雨が降っていた。
雨に濡れながら心の中で何かが弾けた一瞬だった。
芭蕉と曾良が杉風の別荘・採茶庵から、別れを惜しむ門人とともに隅田川を船で千住へと向かい千住大橋の北詰にある千住の船着き場から芭蕉は千住に上がる。千住大橋から日光街道を芭蕉は曾良とともにみちのくへと歩みだす。上野や谷中など江戸名所の桜を再び見ることはいつになるのだろう?いや・・・芭蕉の生きた時代の旅立ちは「みなさん、お元気で、さようなら」と、死をも覚悟した旅であったのだろうと思った。その地で奥の細道矢立初の碑をつくづく見つめた。その時、仕事を忘れ、自分も何かこれまで何気なく過ぎてきた時間を見つめなおしていた。
考えてみれば俳句に触れたのは中学生の時か。再び、俳句を習い始めている。中学生からの時間の経過を考えたら、もう気も遠くなる。だから全くの初心者ということでスタートだ。
これまで、数字やらデータをもとにと記事などを書いてきた自分にとっては全くの未知数である。長年の「癖」のようなものをおいてということでないと前には進まない。いわば...左脳と右脳か?という感じである。君島芝田先生のコツコツとした指導のもと、忘れ去っていたものの見方に気付く。
そんな折に「羅や人悲します恋をして」・・・鈴木真砂女さんの作品を見つけてしまった。羅(うすもの)は夏の季語である。みちならぬ恋。その一途さゆえの悲しさと儚さか。
ああ、蒸し暑さの中に何とも艶っぽい時間が過ぎた。
ch04.カルチャー : 謡講 |
||||
能楽師の山井綱雄和さんがの伝統・文化・芸術を気軽に楽しめる新しい試み白瀧文化祭「謡講」をします。「謡講(うたいこう)」とは、京都の町屋の座敷で屏風や襖越しに「謡(うたい):能の声楽」を鑑賞する文化ということです。夕暮れ時の白瀧呉服店の座敷で蝋燭やお香の中での「謡講」は、きっと今までにない「幽玄」の世界を感じさせてくれます。東京では珍しい開催です。今回は、恋慕の名曲「井筒」全曲を山井綱雄が謡います。先立てて行うワークショップでは、「謡」の魅力を解説。簡単な謡体験・発声も行い、謡の魅力に迫ります。なお和服・浴衣の方は500円割引ということです。
【日程】
2011年7月23日(土)
【会場】
白瀧呉服店
謡ワークショップ「謡の魅力に迫る」
(受講者も簡単な発声体験稽古有り)
7月23日(土)
◆開演 14時
◆終演 16時(予定)
◆料金 2000円
◆出演 山井綱雄、村岡聖美(金春流能楽師)
「謡講(うたいこう)」謡曲「井筒」
◆開演 17時
◆終演 18時半(予定)
◆料金 3000円(和菓子お抹茶付)
◆出演 独吟「田村」 村岡聖美
独吟「藤戸」 山井綱雄
素謡「井筒」 山井綱雄
◆ お申込み・お問い合わせ
白瀧呉服店
TEL 03-3933-0033
ch04.カルチャー : 無間地獄 |
||||
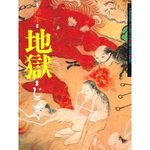 ちょっと絵本について調べることがあって図書館ではなく・・・書店へ。児童書のコーナーで「絵本・地獄」(風濤社)を発見。千葉県安房郡三芳村延命寺に所蔵されている十六幅の絵巻をもとに構成されたもので、天明四年の絵師によって描かれたものだという。勿論、図書館にはほぼ所蔵されているようだが、たまたま平積みになっていて、その迫力につんのめったという感じである。「一体何歳児からの絵本?」と思いしながらページをめくるが、怖い・・・・
ちょっと絵本について調べることがあって図書館ではなく・・・書店へ。児童書のコーナーで「絵本・地獄」(風濤社)を発見。千葉県安房郡三芳村延命寺に所蔵されている十六幅の絵巻をもとに構成されたもので、天明四年の絵師によって描かれたものだという。勿論、図書館にはほぼ所蔵されているようだが、たまたま平積みになっていて、その迫力につんのめったという感じである。「一体何歳児からの絵本?」と思いしながらページをめくるが、怖い・・・・
昔、明治生まれの祖母がよく「地獄」のことを話してくれた。でも話の中に出てくる「血の海」やら「針の山」やらに、「どのくらいの深さの海なの?」「長さはどのくらいの針なの?」といろいろ聞く子どもであつたため、祖母は「もういい加減にお休みなさい」と話をはぐらかされたような思いでがある。
しかし、この絵本の語り口がとにかく怖いのだ。ほんの少しだけだが宗教などの勉強をかじった大人になった今、「無間地獄」のページの怖さは格別。ぞっとする。無間地獄の恐怖とは!賽の河原の絵で子供の積み上げる石を崩す鬼が悲しそうな顔をしていたり、ああ~なんと!
続編に「絵本極楽」があるそうなので、地獄の後は極楽でも・・・
◆写真は絵本のイメージ。小さなこどもにはまだ刺激が強い。6歳からとなっているが大人が読んでもかなり衝撃的である。
風濤社 「絵本・地獄」