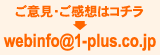ch10.生活: 2010年7月アーカイブ
ch10.生活 : 隅田川の花火 |
||||
ch10.生活 : あさがお |
||||
 暑い暑いと言いながらも四季のある日本にいることを本当に幸福だと思う。例えば、夏至から数えて11目の7月2日頃から7日までの5日間を半夏生と言う。太陽がじりじりと照りつけ始めるとつい忘れてしまうが、この頃に降る雨を半夏雨といい、これは大雨になる。日本の気象の中でこそ実感できる言葉であり肌感覚である。
梅雨もあけると本格的な夏がやってくる。この暑さの中、ふと懐かしい気持ちにさせてくれるのが朝顔。小学校の時の夏休みの宿題で朝顔の観察日記を書いたことがあった。当時はどうしても赤紫色の朝顔が好きで、青紫色の朝顔が咲くと何か落胆していた。今思うと、何故か不思議でしようがない感覚だが。
さて、朝顔に因んだ話であるが、江戸時代になって「変形朝顔」という日本独特の植物が誕生した。これが作られたのは19世紀初期の事であり、まだメンデルの法則が発表される前の事だ。この変形朝顔は園芸家によって特殊な遺伝子の組み合わせで作られたもので、いろいろな資料を見ると、花や茎などはとても朝顔とは思えない摩訶不思議な植物ではある。しかし、当時、この植物は珍重され、高額で売買されたという。そんな中で園芸家たちは変形朝顔を得るために何千ともいわれるほどの苗を処分をした。大切な命を得て、発芽して、愛らしい双葉をつけた苗を処分する時にどれほど園芸家たちが心を痛めたか・・・
雑司ヶ谷に文政9年建立された法明寺があり、そこにはそんな苗たちを供養したという蕣塚(あさがおづか)がある。酒井抱一の朝顔の絵に添えて「蕣や くりから滝の やさすがた」という句が彫られている。その碑の前にたつと江戸時代の人々の内に流れていた自然と共生していく、そんな優しい気持ちを感じることが出来る。
暑い暑いと言いながらも四季のある日本にいることを本当に幸福だと思う。例えば、夏至から数えて11目の7月2日頃から7日までの5日間を半夏生と言う。太陽がじりじりと照りつけ始めるとつい忘れてしまうが、この頃に降る雨を半夏雨といい、これは大雨になる。日本の気象の中でこそ実感できる言葉であり肌感覚である。
梅雨もあけると本格的な夏がやってくる。この暑さの中、ふと懐かしい気持ちにさせてくれるのが朝顔。小学校の時の夏休みの宿題で朝顔の観察日記を書いたことがあった。当時はどうしても赤紫色の朝顔が好きで、青紫色の朝顔が咲くと何か落胆していた。今思うと、何故か不思議でしようがない感覚だが。
さて、朝顔に因んだ話であるが、江戸時代になって「変形朝顔」という日本独特の植物が誕生した。これが作られたのは19世紀初期の事であり、まだメンデルの法則が発表される前の事だ。この変形朝顔は園芸家によって特殊な遺伝子の組み合わせで作られたもので、いろいろな資料を見ると、花や茎などはとても朝顔とは思えない摩訶不思議な植物ではある。しかし、当時、この植物は珍重され、高額で売買されたという。そんな中で園芸家たちは変形朝顔を得るために何千ともいわれるほどの苗を処分をした。大切な命を得て、発芽して、愛らしい双葉をつけた苗を処分する時にどれほど園芸家たちが心を痛めたか・・・
雑司ヶ谷に文政9年建立された法明寺があり、そこにはそんな苗たちを供養したという蕣塚(あさがおづか)がある。酒井抱一の朝顔の絵に添えて「蕣や くりから滝の やさすがた」という句が彫られている。その碑の前にたつと江戸時代の人々の内に流れていた自然と共生していく、そんな優しい気持ちを感じることが出来る。
写真 法明寺の蕣塚(あさがおづか)
ch10.生活 : いやはや・・・ |
||||
普段、ぼんやりと暮らしていると何が常用漢字だったっけ?ということに。特にパソコンが完全に生活に入り込んでしまった今は本当に漢字が書けず「しまった!」が多い。そうなると何が常用漢字だったか?など全く分らなくなる。
29年ぶりに、常用漢字が見直されて196文字が追加されることになった。何気なくというか意識せず、または好きで書いていた漢字ではあるが、こういう機会に改めて「常用漢字か・・・」と思うのだ。
文化庁
ch10.生活 : タラヨウ |
||||
 先般、北新工業の末国社長とお話ししている時に「吉田さん、ハガキのもとになっている葉はなんだと思う?」といきなり聞かれた。いつものように悪戯っぽい目であった。私が答えられずモゴモゴと迷っていると、目の前に一枚の葉が差し出された。「タラヨウの葉だよ~」と仰る。ちょっとさわってみた。肉厚な葉だ。あまり?葉脈は見えない。文字や絵を書くと、その部分がやがて黒くなって浮き上がるそうで、そのまま乾燥すると、この黒い部分はそのまま残り長い間、保存することができるそうだ。この葉に最初に出会って、文字など書いた人「ホーッ!」とかなり感動したんじゃないかな?とまたいろいろ思う。ちょっと調べてみたら、ヤシ科の常緑高木。原産地はアフリカ。インドなどの乾燥地帯で栽培され、高さが20mにもなるという。葉からはムシロ、扇、わらじ、帽子、傘、そして紙?を作るとあるが・・・。葉書の木とも呼ばれたようだ。まあ、本題はこれからの活動であり、広葉樹林が今後の日本にどれだけ大切な存在になるかということだ。その活動のためにも「樹」について勉強が必要ということか!
先般、北新工業の末国社長とお話ししている時に「吉田さん、ハガキのもとになっている葉はなんだと思う?」といきなり聞かれた。いつものように悪戯っぽい目であった。私が答えられずモゴモゴと迷っていると、目の前に一枚の葉が差し出された。「タラヨウの葉だよ~」と仰る。ちょっとさわってみた。肉厚な葉だ。あまり?葉脈は見えない。文字や絵を書くと、その部分がやがて黒くなって浮き上がるそうで、そのまま乾燥すると、この黒い部分はそのまま残り長い間、保存することができるそうだ。この葉に最初に出会って、文字など書いた人「ホーッ!」とかなり感動したんじゃないかな?とまたいろいろ思う。ちょっと調べてみたら、ヤシ科の常緑高木。原産地はアフリカ。インドなどの乾燥地帯で栽培され、高さが20mにもなるという。葉からはムシロ、扇、わらじ、帽子、傘、そして紙?を作るとあるが・・・。葉書の木とも呼ばれたようだ。まあ、本題はこれからの活動であり、広葉樹林が今後の日本にどれだけ大切な存在になるかということだ。その活動のためにも「樹」について勉強が必要ということか!
ch10.生活 : 一日花 |
||||
毎日、茹だる様に蒸し暑い。いつまで続くのかな?と思う頃、毎年気付くのだ。暑い暑いと汗だくの自分が恥ずかしくもなる。
むくげの花が庭にひっそりと咲く。朝に咲いて、夕には散ってしまう、何とも儚い花だ。でも蒸し暑さの中で、そこだけひんやりとした涼感がある。茶花でもあるむくげ。このひっそりとして、陽が沈む頃、ぱたっと散る花は、この蒸し暑い中で凛とした気持ちにさせてくれる。