現役の看護師さんで僧侶でもある玉億妙憂さんの『死にゆく人の心に寄り添う』医療と宗教の間のケアについて読む。
玉億さんは、ご主人が癌になられた時、ご主人本人の意思を貫き、ご自宅での介護と看取りをされている・・・と文章で書くと、単純にそれだけであるが、実際に介護というものを経験してみると、「生」を貫く人間と、そして少しずつその「生」から離れていく辛さというか、なんと表現してよいのか言葉につまるほどの葛藤が分かる。
人は亡くなる数週間から数日前にパッと調子がよくなって意識がクリアになることがあるという。例えば、大好物のものを「食べたい」と言って実際に食べたり、「誰それに会いたい」など。しかし、それはそう長くは続かず体調は不安定になっていくという。もし病院で「家に帰りたい」と言ったならそれは末に帰る最後のチャンスということだ。しかし、実際にはなかなか大変なことだ・・・と私は思う。
実母が亡くなった朝のことを思い出す。「このままだと脳圧が上がる」ということを言われた。そしてその装置を外すかどうするか?と医師の声に対して私は訊いた。その「苦しいと思います」と静かな医師の答えに頷いた。その朝の、病室から見えた青空を思い出す。私を産み育ててくれた母の静かな呼吸が消えた瞬間だった。
死ぬ間際の人のカラダと心の変化。改めて実に不思議な現象だと思い、人間というものの発生はやはり奇跡か!と思える。
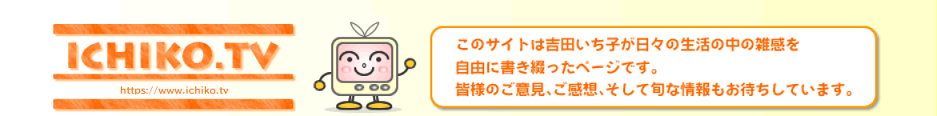

 昨日、「4分間」を意識してしまった話を書いたが、時刻ではいろいろ学んだ。
昨日、「4分間」を意識してしまった話を書いたが、時刻ではいろいろ学んだ。 会議の合間のちょっとした時間に血液型の話になった。随分前から血液型占いなるものは流行っている。とくにB型の人は気の毒(笑)「やっぱり!B型なんだね~」とよく言われていることも聞く。B型にしてみれば「だから何だっていうんだ!」の気分でしょう。
会議の合間のちょっとした時間に血液型の話になった。随分前から血液型占いなるものは流行っている。とくにB型の人は気の毒(笑)「やっぱり!B型なんだね~」とよく言われていることも聞く。B型にしてみれば「だから何だっていうんだ!」の気分でしょう。




