ふわ~っと金木犀(キンモクセイ)の香りに包まれた。この香りが好きという人と嫌いという人が結構わかれる。中には「トイレの芳香剤と同じ」という表現をする人もいる。
しかし9月の終わりころから10月にかけての短期間、この香りがすると何故か安心する。
そして実は、なかなか知られていないが銀木犀(ギンモクセイ)という植物も存在する。香りは金木犀ほどでなく、白い花を咲かせる。
10月はそんな楽しみもある。
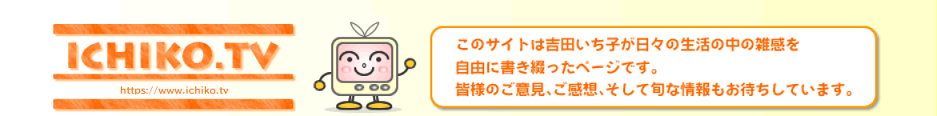
ふわ~っと金木犀(キンモクセイ)の香りに包まれた。この香りが好きという人と嫌いという人が結構わかれる。中には「トイレの芳香剤と同じ」という表現をする人もいる。
しかし9月の終わりころから10月にかけての短期間、この香りがすると何故か安心する。
そして実は、なかなか知られていないが銀木犀(ギンモクセイ)という植物も存在する。香りは金木犀ほどでなく、白い花を咲かせる。
10月はそんな楽しみもある。
今どきの子どもたちは「公衆電話」を知らず、そして「かけられない」という番組を見て、なーるほと!そんな時代なんだと思った。まず電話ボックスにどうしたら入れるのか?もまごつき、10円玉を受話器を外さずかけてみている。10円玉がコロンと落ちてきて「かけられなーい」と言っている姿。あああ、こんな時代かと思った。
もう生活の中では身近なものではないのだ・・・と思いつつ、2011年3月11日の東日本大震災の時の駅の様子がうかぶ。街中の人々は必死に公衆電話の前に並び、必死だった光景だ。スマホも何もかも通じなかったあの日。都心の交通は麻痺し、メールも何も無理だった。公衆電話に人々は群がっていた。公衆電話の少なさに嘆きも聞いた。電話番号がスマホに入っている人は番号の検束も出来ず右往左往していた。どうしようもない脆弱さを見た。
そのうち、ツイッターの呟きを信じた人たちが騒ぎ出したのだが、私はどうも信用出来ず何とか、パソコン通信は出来ないものかと。原稿締め切りに間に合ったものの先方だって右往左往しているに違いないと思った。本当に手も足も出ないという時に、手帳にメモしてあって公衆電話を使える人がどんなに優位だったか、目の当たりにした。
公衆電話・・・そしてダイヤル電話、プッシュ電話もあった。端境期というのだろうか、全く知らずその「時代」を生きていくしかないのだと思った。
ふっと・・・スマホもない時代が思い出された。歌謡曲はそんな「時代」を如実に語る。
松山恵子の『お別れ公衆電話』は「♪汽車に乗ろうと 思ったものを駅の喫茶の公衆電話 いつかかけていた」と切ない女ごころを歌い、小山明子の『恋に落ちて』では 公衆電話ではなく自宅の固定電話だろう。「♪ダイヤル回して 手を止めたI’m just a woman Fall in love」と歌う。切ない女心には「公衆電話」は必須アイテムだったのだ。今なお、スマホの中でその女心は現役であると思うが・・・
公衆電話や自宅固定電話ではないが、コミュニケーションツールの一つとして野口五郎の『私鉄沿線』では「♪伝言板に君のこと 僕は書いて帰ります」とある。当時、駅には伝言板というものがあって、そこに「先に行く」「1時間待った」というような短いMESSAGEが書かれたものだ。時折、その内容の面白さに暫く立ち止まって読んでいたこともあった。心情を吐露するものもあった。
しかし、今どきの若者にはこのような世界は「古典文学」なんだろうなと思うと何か笑いがこみ上げてきた。いずれは、スマホを中心として、ラインだなんだかんだも「古典文学」の世界になるのだろうかって。
ただ、〝以心伝心〟は、太古から未来まで永遠かなと思う今日この頃である。
まるで学術書を読むような名前が並ぶ昨今のクリスマスケーキ。流通さんの世界ではいよいよ「予約会START」である。そのケーキは「食品」というより「芸術品」の世界である。これをクリスマスケーキとよんでよいのか?と思うほどである。多分、どこからナイフを入れていいものやら、眺め続けてしまうのではないかと思う。微妙な繊細な味のハーモニー?へ誘われる。
素朴な手作りの昭和のクリスマスケーキが妙に懐かしくなってきた。ジングルベルの曲にのって浮かれたお父さんたちが「これだ!」という気分で家族サービスした一品でありそれは当時、逸品だったのだろう。凝った家ではマルドリを焼き、七面鳥を焼く家もありも本当にそれぞれの家庭の味とその一品でより華やかになったのだと思う。勿論、料理上手のお母さんは手作りケーキで子どもたちが飾りつけに大騒ぎしたのだろう。
しかし・・・
クリスマスケーキにしても、おせち料理にしても然り。「おせち料理」というよの「正月の料理」とでもよんでほしいと個人的にしい毎年思っている。その思いは年々強くなっている。自宅でおせち料理など作る家がだんだんとなくなってきているのは確かだと思う。今では何万もいえ、何十万もするおせち料理セットというものが売れて且つ人気商品である。
記事を書く筆がとまってしまうのは「おひとりさまおせち料理」というものに初めて出会った時だった。おひとり様ビジネスはますます活気をみせている。あるところまで止まらないのだろうな。
この季節になると本当に考えさせられる。「家庭の味」「お母さんの味」っていうものの世界が昔とは確実に違ってきているなと。あるテレビコマーシャルでは「お母さんの料理が食べたくなった」と実家に帰ってきた息子にコンビニで買ったレトルト食品を並べる母親。ある日、そのコンビニで買い物をしている息子とばったり!「お母さん!」と叫ぶ息子と逃げる母。ふふふと笑うコマーシャルではあるが、笑えない。ある家庭では毎日レトルト並べている奥さんがいてご主人は料理上手の奥さんを嫁にもらったと大喜びしている家庭もある。その嫁が「メニューに限界」と言って悩む。これ現実の話。
一生、料理しないでも生きて行ける世界も今後はありだなって。
でも、この地球上では当たり前のように飲んでいる安全な水も飲めない人々がいる。彼らはレトルト食品も知らない。嗜好品をたっぷり知っている私たちとはあまりにもかけ離れた世界なのだ。
中央図書館の担当者の方から連絡。地域文化ゼミの申し込みが今日からで、何と出だし好調!とか。嬉しいですねぇ。毎年毎年、いつもなんらかの変化にぶつかり、それがまた弾けている、そんな感覚である。今、出来ることを一生懸命にしよう!と思う。
それにしてもスポーツ業界のパワハラ、各界の異変、有名歌手の相続トラブル、そして日本の貿易赤字。問題点出せといったら本当に限りなくこの世の中ってあるな。
発生から発展へ
都市のエネルギーを探る
「池袋の~マーケットから駅ビルへ~」
10月20日(土)と11月3日(土)の2日間、いよいよ平成30 年度 豊島区立中央図書館の秋の地域研究ゼミナールが始まる。以前、ブログにも書いたのだが「池袋の~マーケットから駅ビルへ~」のゼミである。池袋という地域だけではなく、戦後のヤミ市というものが一帯何であったのか?現在の都市形成にどんな影響力があったのか?こんなところを探っていく。ヤミ市の発生と変化、その中で生まれた池袋の都市としてのエネルギーに迫っていく。汚い、怖いなど言われた池袋という都市。カルチャー都市というほどに変革し成長を続けている。
第1回では、戦前の池袋、戦災を受けた池袋を地図や写真から確認したうえで、戦後の池袋の復興過程を見つめる。ヤミ市の誕生、そして発展。資料や証言から迫る。
第2回では、ヤミ市によって仮設的な建物で復興を遂げた池袋が、戦災復興都市計画によってどのように変化し、現在につながる巨大な商業都市となっていったのか、特に駅ビルに注目して明らかにする。
今回は東京理科大学工学部建築学科助教の石榑督和さんとともに進めて行く。
チラシも配布されているため、既に申し込みがフライングしていると聞いたが、明日9月25日(火)スタートである。同内容ではないので出来れば1回、2回と連続して受講をお勧めする。貴重な資料も用意する予定である。
第1回 「ヤミ市の発生」
10月20日(土) 午後2時~4時
第2回 「ヤミ市から駅ビルへ」
11月3日(祝日・土) 午後2時~4時
【会場】 豊島区立中央図書館5階会議室
【定員】 申込先着40名
【受講料】 500円 ※初回にいただきます。
【申し込み】 9月25日(火)午前10時より
氏名・住所・連絡先(電話番号とメールアド レス)を明記の上、電話、FAX、メール、直接来館のいずれかの方法で下記担当までお申し込みください。
【担当】 豊島区立中央図書館企画調整グループ
電話:03-3983-7861
F A X:03-3983-9904
メール:A0027900@city.toshima.lg.jp
 このところ休みがなく・・・
このところ休みがなく・・・
心がザワザワするほどの忙しさだった。
ほっとした日曜日。
時間の感覚がよみがえった。
ふっと、近くの家の花壇にあるオシロイバナが目に入る。
鮮やかな赤色。
お寺の鐘のような黒い種子をつぶすと、白粉のような白い粉が出てくる。子ども時代、よくそれを頬につけて遊んだものだ。
オシロイバナは別名「夕化粧」。
その名の通り夕方から開花する。
名づけ親は江戸時代の博物学者、貝原益軒。
虫たちは夕方頃からその色や香りで引きつけられてしまう。
兎に角、繁殖力が強いオシロイバナは夕方から妖しく香りを放つのだ。
自然に気をとられていると、溜まった疲れがほぐれていく。
9月20日午後1時過ぎ、自民党総裁選挙の投開票が行われた。
開票の結果、空気は「もうわかっている」という中、安倍総理大臣553票、石破元幹事長が254票となり、安倍総理大臣の3選が確定した。、
が・・・である。
地方票については、安倍総理大臣がほぼ圧勝と見られていたものの、なんと石破氏が地元の島根で圧勝したほか、群馬・茨城・三重・富山・高知・徳島・宮崎など7県でも上回り、石破氏の存在感を示す結果となった。ここがミソである。
暫くご無沙汰している女流画家のCさんから絵画展のハガキが届いていた。何か・・・画風というのだろうか?イメージがすっかり変わってしまっていることに気付いた。もう数十年も経つのだから「変化」はあるものだと思うが、視点というか、やはり変化している。一言でいうと、これまでは、弾けるような明るくて華やかなものだった。デフォルメも明るいタッチだったと思う。今回の作品は実に写実的。今までは描かれなかったように細かでふと見落としがちなところに絵筆が極まっている、そんな画風だ。
カレンダーとにらめっこ。都合がついたら是非、伺って話を聞いてみたい、そんな気持ちになった。
俳優の樹木希林さんが9月15日に亡くなっていたことわかった。享年75歳。
確か、5年前か?全身が癌であると発表をした。しかし、信じられないほどの演技の数々を見せてくれた。
映画『万引き家族』ではあまりにも気持ちが悪いというか・・・すざまじいというか・・・「何だろう?」と思っていた。なんでも入れ歯を外して、食事風景は歯茎でしごいていたというから、またまた驚いた。
「始末」というか、「何もほしくないのよね」と語っている番組では古着をリメイクしたり、布切れも最後の最後までキッチンの掃除に使ったりしている姿は潔さを感じた。それに・・・お墓も桜の見える良い場所で、しっかりと掃除をしていたというから、何か不思議な驚きとともに尊敬にあたいする気持ちだ。マスコミへの対応もすごい。記者会見のための部屋も自宅に用意したりと何もかもが公平だったという。
最近、周囲で「終活」と騒ぐ人が多いが、どうも「やり残したことが多すぎる」ようで、煩悩からは逃れきれない。「あれもしたい!」「これもしたい!」と、まだまだその域にはたっしていない人々だ。「やればいいのに」と思う。
やはりその人に与えられた「寿命」というものがあり、何も人生100年時代と興味も関心もないのに礼賛する必要もないだろう。
とにかく、樹木希林さん。芸名からしてもあっぱれであるが生き方も素敵だったなと思える。どうぞ、安らかに・・・