梅雨があけたとか?梅雨らしい日が無かった気がする。いきなりの土砂降りに久しぶりにコンビニに飛び込んでビニール傘を買った日が一日あったが、本当に猛暑猛暑の日だったと思う。
今朝も用事があって外に出たもののまさかのふらつきで早めに帰宅した。温暖化なんてものじゃない年がつづくのではないか?40度なんてふつうにあって、夜はとんでもなく寒くなるとか。これまて経験したことのない日々ではないかしら?
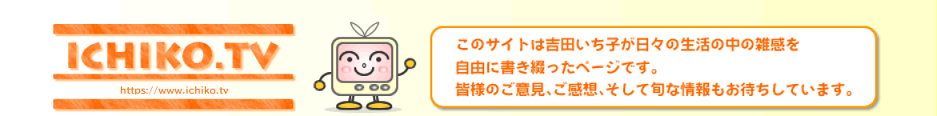
梅雨があけたとか?梅雨らしい日が無かった気がする。いきなりの土砂降りに久しぶりにコンビニに飛び込んでビニール傘を買った日が一日あったが、本当に猛暑猛暑の日だったと思う。
今朝も用事があって外に出たもののまさかのふらつきで早めに帰宅した。温暖化なんてものじゃない年がつづくのではないか?40度なんてふつうにあって、夜はとんでもなく寒くなるとか。これまて経験したことのない日々ではないかしら?
梅雨入りはしたと思ったが・・・本日の暑さ。東京は35度と聞いた。役所の事務処理もあって、やはりバタバタと外出するものの、肌に切り込むような暑さ。6月でこんな暑い日ってあったっけ?不思議になる。6月少しと7月と8月。そして9月も残暑か?イベント実施の事を考えると胃痛がする。
2025年も梅雨入りしたみたいね(笑)どうも今年は雨の少ない梅雨だというけれど。「雨が多くなりそう」と言う事も聞いたし、これまたどうなるか分からない。
以前、誕生会で鉢植えの紫陽花をいだたいた。それは弾けるように可愛らしい紫陽花で「ダンスパーティー」という名前だったかと思う。地植えしたが、あまり咲かない年が続いたものの、今年は何とも❢植物の命を感じる。
梅雨は梅雨、それなりに雨好きの私としては愉しみもある。
10代の頃は『車輪の下』など夢中になって読んだものだが・・・ヘルマンヘッセの「老齢について」のエッセイを読み始めると、見透かされた?がごとく、理解者に出会った気持がちした。まさか・・・であるが人は加齢していき、そんな理解者に出会った気持ちだけでも幸せな事である。
時間としてはほんの数秒の景色だった。
車窓から、ビル建設の風景が見える。50階をゆうに超す高さのビルと聞いている。ふっと・・・数秒。その地面の下には遺跡があって、工事が随分と遅れたと不動産屋がいろいろ言っていた日を思い出した。
その遺跡の現地案内会が1日だけ特別に開かれた時、そこにある縄文時代の穴や、江戸時代の住居あと、そして、近代に入り、有名企業の最初の工場あと、関東大震災での被害状況・・・いろいろ見学した日の事を思い出した。
高層ビルが建った後、そこで仕事を仕事をする人も暮らす人も、みんななーーーーにも知らないで生活が営まれていく、そんな事を考えていると、その風景は眼前から過ぎ去ってしまった。
愉しい一日の数秒の時間旅行だった。
最近は「時」の流れをビシビシ感じる、
新宿東口で待ち合わせ。ぼーっと「新宿アルタ」を見つめた。なんでも2月28日に閉店するという。もうすぐだね。
1980年に開店した「新宿アルタ」。取材に行った日の事を思い出した、「オルタナティブ」が由来だと担当者から聞いた、とにかく新しいものを発信していく❢という位置づけ。7階8階には「スタジオアルタ」があり、新しいものを発信していくという位置づけだった。タモリの人気番組「笑っていいとも」がスタートした。
そうか、32年間か・・・確か、最初の番組も拝見したと思う。
なんかね・・・「時」が凄い勢いで流れていくよ。不思議感覚でいた。
仲間たち集合‼ もっと古い時代の話にはながさいたよ。なんてこった‼(笑)
昨日、節分には豆まきをして、今日は「立春」。二十四節気において春の始まりとされる日。
いよいよ❢2025年がスタートする。
ああ、この日まで少し長かったな・・・よし❢春が来た。