先般、某所でマーケテイング講座を受けた。
神戸の老舗のパン屋さんの「イスズベーカリー」と「ケルン」の三代目が講師だった。二人とも若くて斬り込み方と意欲がビシビシ伝わってきて何とも心地よい講座であった。
シュトレンを試食した。街にクリスマスツリーが現れるとパン屋さんで、ケーキ店でなどでシュトレンが登場する。日本でも浸透したなと思う。
シュトレンとはドイツ発祥のクリスマス菓子。表面に粉砂糖などをまぶした、ゴツゴツした見た目が特徴的。中身は、小麦粉生地を発酵させたパン菓子で、ドライフルーツやナッツなどが練り込まれている。もともとはキリストの誕生を待つ4週間の待降節(アドベント)の期間に少しずつ切って食べるもの。そしてその間に味が徐々に変わっていくのが楽しめる・・・というものだ。
「食」の中で息づいている文化を感じる日々だ。
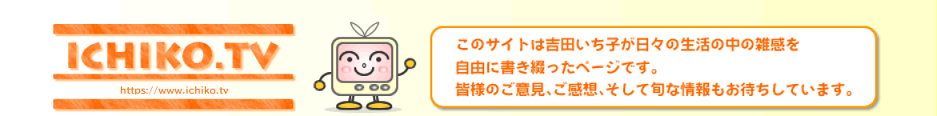
 写真はウイスキーをのみちらかしているわけではないのです・・・(笑)
写真はウイスキーをのみちらかしているわけではないのです・・・(笑)

 本日は2019年6月25日。
本日は2019年6月25日。
 ひなまつりは春のかおりがする。
ひなまつりは春のかおりがする。




