 やたらと店先で「晩白柚」(パンペイユ)が目立つので買う。晩白柚は「大きい!」というほどの柑橘類である。いざ!むこうとするとなかなか手ごわいのだ。皮がかなり分厚くて、むくのが容易ではないのだ。
やたらと店先で「晩白柚」(パンペイユ)が目立つので買う。晩白柚は「大きい!」というほどの柑橘類である。いざ!むこうとするとなかなか手ごわいのだ。皮がかなり分厚くて、むくのが容易ではないのだ。
一つ目の晩白柚の時は、「もったいないなぁ~」と思いながらも皮を捨てた。しかし二つ目の時は「そうだ!ジャムを作ってみよう」という気持ちになった。むいた皮の白い部分は少しこそぎとり、薄く皮の部分を切る。それを一晩、水に晒し、そしていよいよ煮込んでいく。種も捨ててはいけない。ここからペクチンが出るそうなので、夏に冷茶を作る時、茶葉をいれる袋に種を入れて一緒に煮込むのだ。とにかく焦らずコトコトと。
中身は爽やかな酸味で本当に「わおっ」というほどに美味しい果物だ。この房に出あうために分厚い皮を突破しなくてはならないのか?と思うほどに美味しい果実である。
なかなか・・・ジャムらしくならないが・・・忍の一字で優しく丁寧に煮込んでいくと出来上がる!
さてさて・・・トーストか?と思って舐めてみると、ヨーグルトの上にのせて食べたらうまかろうという気持ちになる。柑橘の香りとほろ苦さがたまらない。多分、苦みに弱い人は多分無理だろうが・・・
このところ、朝食にはヨーグルトに晩白柚ジャムをのせる。うまい!
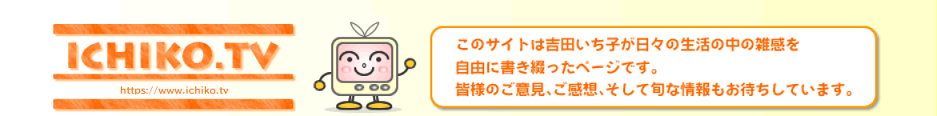
 BARでカクテルを味わった。青じそベースのカクテルで、実にすっきりした味わい。大葉はつまみながら・・・
BARでカクテルを味わった。青じそベースのカクテルで、実にすっきりした味わい。大葉はつまみながら・・・ 梅雨って・・・なんか青梅を漬けたくなる。梅酒を作ろう!と思い立って、静かに丁寧に青梅のヘタをとる。こつこつと・・・こおり砂糖と焼酎とのハーモニー。あとは楽しみに待つだけである。
梅雨って・・・なんか青梅を漬けたくなる。梅酒を作ろう!と思い立って、静かに丁寧に青梅のヘタをとる。こつこつと・・・こおり砂糖と焼酎とのハーモニー。あとは楽しみに待つだけである。




