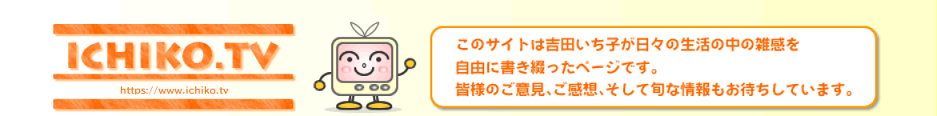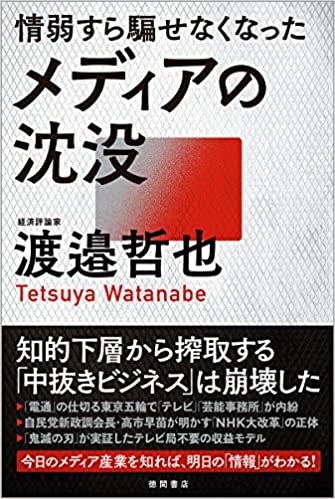‘ch11.経済’ カテゴリーのアーカイブ
2022 年 1 月 30 日 日曜日
毎年恒例の「社会貢献活動見本市。今年こそ!会場に来場者があっての展開をと思っていたが、このコロナウイルスの蔓延により、リアル開催ではなくなった。何とか・・・と出展説明会の時は希望もあったのだが、会場での開催は無し!と決まってから、本当にどんよりした気分になった。気持ちというより気分である。リアル開催ならではの展開案だけで一杯だったので、それがダメとなるとと思うと日々何とも表現出来ない胃痛である。動画上映でやりますから~というのであればそれこそ、「これでもか」というほどのインパクトを持たないと全く無策となる。考えれば考えるほど胃が痛む。「ケセラセラよ~(^^♪」などと対面的にはいうが、そんな簡単なものではない。またまた呻吟・・・・
一体、このコロナの蔓延はいつまで続くのだろうか?3年目に突入したからこそ次の2023年、2024年・・・といろいろ考えてしまう。巷には都市伝説というのか、環境破壊により地球が・・・となんとかかんたかクライシス情報が氾濫している。全く見えてこないのも実情である。
百貨店さんも「ちょっと・・・」と悩みを聞くが居酒屋さんの落ち込みが激しい。自分が居酒屋経営していたらもうどうしようもなく迷っていると思う。ひとつずつ冷静に情報分析をする。「価値観が変わる~」などとカッコつけていう人も多かったが本当に呻吟だ。カンタンに物言うな!である。
カテゴリー: ch01.政治, ch02.健康, ch04.カルチャー, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2022 年 1 月 12 日 水曜日
なんとか行けるか?!・・・と思って、税務署へ。諸々相談もあったので。確定申告終了。ああ、ほっとした・・・それにしても最近はスマホ一台て全て完了した!あらためて凄い時代になったものだと思う。
カテゴリー: ch10.生活, ch11.経済 | コメントはまだありません »
2021 年 12 月 9 日 木曜日
全く真実というものが分からない。ただ、武漢のコロナウイルス初症例から2年という月日が経ったことは事実である。しかし中国の習政権はその「起源説」の幕引きを図り始めている。オミクロン・・・そして多分、今後もギリシャ文字が不足するのでは?と心配するほど。
ただ、当初からどうも日本人の感染が他の国とは違う、これは何だろう?と思っていた。密かに思っていたのだが・・・つまり周囲の人々でそれを感じた人はいなかった。日々発表される感染者数に拘っていた。しかたないなと思っていた。
しかし、日本人の新型コロナウイルス患者が例えば欧米人とは確実に少ない。謎の「ファクターX」について理化学研究所の発表<2021年12月8日>に「やはり」と思ったかなり専門用語でかためられているが、要は日本人に多い<約6割>特定の免疫のタイプということだ。感染した細胞を免疫細胞の一つであるキラーT細胞が破壊する仕組みも判明したという。あらたに脅威は続くが、オミクロンに対しても有効なワクチン開発につながるようである。
しかし・・・また疑問。なんで、日本人はその免疫を獲得したのだろうか?
カテゴリー: ch02.健康, ch10.生活, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2021 年 11 月 29 日 月曜日
たぶん人間対ウイルスはえんえんと続くのかと思う。南アフリカで確認された新たな変異ウイルス。WHO=世界保健機関が110026日、現在、広まっているデルタ株などと同じ「懸念される変異株」に指定し、「オミクロン株」と名付けた。しかしギリシャ文字がなくなるのでは?と変な心配までしてしまった。デルタ株に比べて感染の速さが5倍くらい速いそうだ。香港、それにイスラエルで感染が確認されたほか、ヨーロッパではイギリス、ドイツ、ベルギーに続いてイタリアなどでも確認された。日本は大丈夫!ということはないと思う。またも緊急事態宣言か?
カテゴリー: ch02.健康, ch10.生活, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2021 年 11 月 16 日 火曜日
大手の新聞社関連の旅行会社から、そしてこれまた大手の出版社の通販部門からの通知。毎回、練りに練った企画力のこんだ内容であり、また通販の商品も逸品と言える数々だった。「ああ、時間作って、是非ともツアー参加したい」「買おうかなと」と思える商品構成だった。しかし届いたのはどちらも「事業中止」のお知らせである。旅行企画は2022年1月出発分まで、通販は2021年12月31日までの申し込みとなっていた。残念・・・などという言葉では言い表せない気持ちである。
コロナの第6波の心配や不安の中でも随分と明るい光がさしこんできたかと、活動開始しているようであるものの、やはり「時代なのか?」としか言葉が出なかった。新生!ではないのか、いや、絶対に次は来る!と私はは信じているのだが、どうも抗えない地球規模の力が働いてしまっている感じがする。
カテゴリー: ch04.カルチャー, ch08.旅, ch10.生活, ch11.経済 | コメントはまだありません »
2021 年 11 月 10 日 水曜日
情弱すら騙せなくなった・・・こんなフレーズに・・・
経済評論家の渡邉哲也氏の「メディアの沈没」を読み終わった。
第1章 切り裂かれたメディアのビジネスモデル
第2章 「東京五輪」を裏切った テレビ局
第3章 護送船団の 沈没プロセス
第4章 高市早苗の NHK改革
第5章 新聞はもう死んでいる
第6章 電通弱体化が突きつける課題
新聞社にいた人間としてはいろいろ判っているつもりでも「新聞はもう死んでいる」と言われ速報は遅報となった・・・までは判るがランチェスター方程式の臨界点を突破したとなると口ごもる。「日本ABC協会」の仕事もしたことがあるし、十分に販売数について認識していた。しかし、販売数の伸び悩みの中でも必死に次の未来を考えた。社会に対する影響力まで数値で算出されれば頷いてしまう自分もいる。
しかし沈没とは・・・うまいタイトルをつけたものだ。
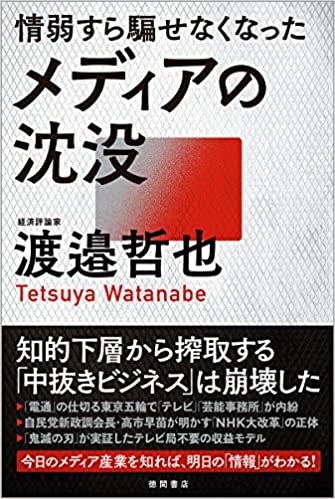
カテゴリー: ch01.政治, ch02.健康, ch04.カルチャー, ch11.経済 | コメントはまだありません »
2021 年 10 月 27 日 水曜日
今年の冬はかなり寒さが堪えると思われる。電力不足なんて考えた事なーい!という人も多いだろうが、なんでもかんでも「湯水のごとく使う」という表現はいずれ無くなると思う。不足・・・不測の事態である。
経済産業省が10月26日の有識者会議で、今年度の冬の電力需給についての見通しを公表。10年に1度の寒さを想定した場合の需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が東京電力管内でなんとギリギリらしい。全国7エリアで3%台、つまりこの数字は「過去10年間で最も厳しい」という事。
電気はいつもたくさん使い放題!ではない事を身に沁みないと分からないのかも知れない、人間って。いつもいつも見ている「スマホ」だって電気がなければ使えない。いろいろ家の中を見回すと、あらら・・・電気なくなったら殆どお手上げ状態となる。
物の大切さって本当になくなってから分かるものなんだろうな。そのためにどうしたら良いのか?どういう方法をとったら良いのか?誰もが「わたくしごと」として考えるんだ!ということ。
カテゴリー: ch10.生活, ch11.経済 | コメントはまだありません »
2021 年 10 月 6 日 水曜日
ことしのノーベル物理学賞に真鍋淑郎さんがドイツとイタリアの研究者とともに受賞された。そのニュースを耳にして本当に本当に嬉しく思った。
大気と海洋を結合した物質の循環モデルを提唱し、二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化に影響するという予測モデルを世界に先駆けて発表した方だ。
現在はプリンストン大学の上級研究員でアメリカ国籍を取得している真鍋淑郎さん。御年90と聞き、またまた驚いた!しっかりとした説明と笑顔。ああ!なんと!とまた嬉しくなった。日本人でノーベル賞を受賞するのはアメリカ国籍を取得した人を含めて28人目、物理学賞では12人目になる。
それにしても二酸化炭素の地球温暖化について予測されていたという研究には拍手!研究されていた時代、決して理解されない事も多々というか・・・そんな時代を切り抜けられて科学で我々に証明して下さったのだ。
カテゴリー: ch04.カルチャー, ch10.生活, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2021 年 9 月 22 日 水曜日
ふと10年後の世界を考えていた。
「進化するテクノロジー同士が融合する「コンバージェンス」により、テクノロジーは加速度的に進歩しているのだという。コンバージェンスは破壊的なイノベーションをもたらし、社会を大きく変えていく。たとえば、スマートフォンの登場はごく最近のことだが、私たちの生活を一変させてしまった。カメラや地図、電話、メモ帳、ゲーム機など、多くの機能が標準装備となり、多くのものが必要なくなってしまった。破壊的なイノベーションは市場そのものを破壊する影響力を持つ。今後も、私たちは次々とコンバージェンスから大きな影響を受け続けることになるだろう。」
こんな一節を読んだからか?
あるイベントの参加者募集方法で改めて「盲点」に気づかされた。「QRコードなんてできないよ!と叱られた。「FAXがないよっ」と叱られた。大半の人はインターネットで申し込みしてくださるが、対象の年代そのものの幅によってひらきがありすぎるのが現代。
実に混沌としている2021年・・・もしや、2020年の記憶かぶっ飛んでいるからか?
今後の10年後に対して、何故かワクワク感が生まれてこない。どうしたものだろう。遺すもの、見失ってはいけない・・・いろいろ考えればかんがえるほど・・・冷静にコツコツ進もう。
先ずは健康でボケないで生きていられれば!
カテゴリー: ch01.政治, ch02.健康, ch04.カルチャー, ch05.エンタテイメント, ch06.音楽, ch10.生活, ch11.経済 | コメントはまだありません »
2021 年 9 月 20 日 月曜日
ある方から『東京の生活史 』岸 政彦 編集を読むとていいのでは?と勧められて早速注文した。50人が語り、150人が聞いた、東京の人生という内容である。〝いまを生きる人びとの膨大な語りを一冊に収録した、かつてないスケールで編まれたインタビュー集〟とあったが届いて実際に手にしてみるとその膨大さというか、ずっしり感ら驚く。広辞苑の重さ?と単純に思ってしまった。
……人生とは、あるいは生活史とは、要するにそれはそのつどの行為選択の連鎖である。そのつどその場所で私たちは、なんとかしてより良く生きようと、懸命になって選択を続ける。ひとつの行為は次の行為を生み、ひとつの選択は次の選択に結びついていく。こうしてひとつの、必然としか言いようのない、「人生」というものが連なっていくのだ。
その解説にある通り。一人一人の人生のなんと重みがあるものかと。自分の人生も時としてちっぽけだな・・・と思うことしばしば。でも、今、自分がこうして生きていることは、何とも途方もない祖先の連鎖によって出来上がっていることに気づく。
この書籍に向かうには・・・少し気持ちをたいらにして・・・

カテゴリー: ch04.カルチャー, ch10.生活, ch11.経済 | コメントはまだありません »