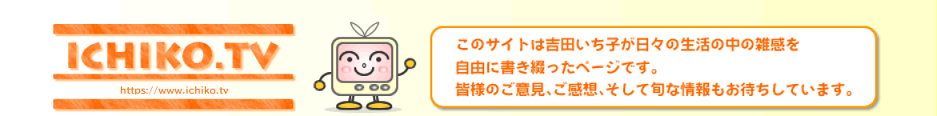‘社会問題’ カテゴリーのアーカイブ
2024 年 2 月 19 日 月曜日
どうも腹の底でモヤモヤしている。ロシアの刑務所で、反体制派指導者のアレクセイ・ナワリヌイが亡くなった。それも突然死。遺体の引き渡しも拒否されているという。
2020年8月にも毒殺未遂事件があった。一時意識不明の重体となり、欧米がプーチン政権による毒殺未遂疑惑を指摘していた。当時、ドイツ政府もロシア政府の関与を強く示唆していた。
身柄拘束後も獄中からネットを通じて、プーチン政権の批判など情報発信に取り組んできた。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻を巡って、「平和のために戦おう」と侵攻に反対する抗議デモの開催をもSNSを通じてロシア国民に呼びかけていた。そんな矢先である。
闇が深すぎる。
カテゴリー: ch01.政治, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 2 月 16 日 金曜日
2024年2月16日の東京株式市場は、アメリカの株高を背景に買い注文が膨らみ、日経平均株価は、一時700円以上値上がり。なんでも34年ぶりに3万8800円台へ。1989年・・・猛烈に記憶している年だ。この年の12月の史上最高値に迫る展開となっている。ああ、不思議な感覚・・・株式にかかわっていないとピンとこないものだと思うが、どう大衆の生活ら影響がでてくるのか。取り引き開始直後から半導体関連の銘柄などに買い注文が集まったとか。熊本県の菊陽町もバブルの風が吹いているのも分かる。
カテゴリー: ch02.健康, ch10.生活, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 2 月 15 日 木曜日
アクセルとブレーキを踏み間違えた・・・高齢者による暴走事故に巻き込まれたた人々の突然の「死」、そして、小さな子どもたちへの家庭内ネグレクト問題。魂の叫びが聞こえるこのニュースは本当に本当に胸の奥がひりひりと痛む。運転に自信がなくなったというより、人が高齢になるという事は次第にあったものがなくなっていくという事があるという事実。そして「プライバシー問題」だと介入を避け続ける事はあってはならない事なんじゃないか?政界の裏金問題を炙り出すのも必要な事かも知れないが・・・暗いニュースがいきばのない怒りと悲しみにかわる。
カテゴリー: ch01.政治, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 2 月 8 日 木曜日
昔から、二月は「逃げ月」とかいうけれど、何とも!実に予定ぎっしり、締め切りぎっしりが続いている。先般、ある女性から「請けるからいけないのよ!」と語気荒く言われたが、別にホイホイやつているわけではない。少しでもステップアップしていかないと人生って実に短いと思える日が多くなっていった。たんたんと冷静に健康とバランスとってステップアップしていきたいだけ・・・という事でてある。
しかし「逃げる」と言えば、最近の国会答弁。誰?!という事ではなく、「なんなんだ!」と叫びたくなる。実に日本の未来がこの政治家だちにたくしていてよいのだろうか?と不安の海に突き落とされていく。なんという!体たらくな問答が続く。
人生にタラレバはないが、自分が、もし政治家を目指して、幸運の女神に守られて、政治家になってまつりごとに一生懸命になったとしたら・・・とふつふつ考えることが多い。やはり周囲に、おかれた環境に、付き合った人々につまっていくのだろうか?って。まあ、いろいろ考えてもしかたないが、何にか社会へ貢献できること、人々に貢献できることを真摯に考えていく態度は持ち続けたいと思っている。
カテゴリー: ch01.政治, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 1 月 30 日 火曜日
人生なんて人それぞれだから、つべこべ言う必要なんてないのだけれど・・・
この人の50年って?と思ってしまった。考えてしまった。
1974~75年の連続企業爆破事件のうちのひとつに関与したか?で指名手配されている過激派「東アジア反日武装戦線『さそり』」メンバー、桐島聡容疑者(70)とみられる男性が1月29日の朝に入院先の神奈川県内の病院で死亡した。なんでも末期がんを患っていたらしい。
50年近くにわたる逃亡生活。偽名で暮らし、飲み屋でのんではギターを弾いたり歌ったりしていたとニュースが報じている。DNA鑑定は判明したのか?本人と確認された場合、公安部は書類送検などを検討されてeるが・・・。逃亡生活50年とは・・・罪は罪である。深い罪である。
カテゴリー: 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 1 月 25 日 木曜日
梅の季節か・・・
税務署へ確定申告。会場で順番か・・・と思っていたら「LINE予約しましたか?」ときた。「いえ」というと「LINE予約の方が優先です」ときた。当日券とかいう紙の時間はあくまで目安であるという。昔流表現で言えば、ガチョーン!であろう。且つ予約者がきた場合は時間がずれるから、時間潰してきた下さいとかなんとか。おいおい‼何言っているの?と。全く、怒髪天に近い感情(笑)「はいはい」といいながら、つぶす時間なんてないよ!とスパッと切った。そして、別件をこなすことにした。
そしてサクサク終わられたいので、今日も参上いたしまして、ライン予約通りの時間にサクサクと。やはり簡単なようで難しいところもある。スマホ操作で分かった事は「慣れる事」につきると。そうすればいとも簡単な作業ということである。
税務署の確定申告終わり、あと一つ企画申請書あげれば何とか1月はOKである。
お疲れ様でしたぁ~
カテゴリー: ch10.生活, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 1 月 19 日 金曜日
ちょっとPRです。
いつもお世話になっている「市民防災まちづくり塾」が「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議」の事務局を担当することになった。詳細は下記。
https://www.tokyo-world-conference.com/index.html
この国際会議は関東大震災から100年、明治43年の東京大水害の再来を防ぐために建設された荒川放水路通水から100年の節目を迎える今、東京の様々なリスクを明らかにし適応していくことで、東京を強靱とし持続していくことが日本のみならず世界の平和と経済に貢献できると考えています。
① この国際会議に是非ご参加ください。東京が直面するリスクを認識し、同様のリスクに世界がどのように適応しているかを知る会議です。事前登録制です。
② 市民の自由意見や専門家の日ごろの研究など分野を超え、立場を超え広く自由にご投稿ください。そのためにこの国際会議は「水都東京・未来会議」「NPOあらかわ学会」「市民防災まちづくり塾」の3者が実行委員会を結成して行う市民会議です。「荒川放水路通水100周年記念市民事業」として実施する市民会議です。
カテゴリー: ch01.政治, ch02.健康, ch04.カルチャー, ch10.生活, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 1 月 14 日 日曜日
能登大地震の傷跡。家が倒壊し、そして声かけあって避難したにも関わらず、高齢の親後さんが津波にのまれ・・・何なのだろう、2024年の元日の事実。何も出来ない自分がいる。自分が出来る範囲での募金活動。その他は・・・
あの見事な輪島塗の作業場も被害をうけた姿。昔、輪島を訪れた時、輪島塗のあまりの美しさに心がうきあしだったくらい・・・凄い芸術だと思った。
さあ自分の出来る事を探していこう。
カテゴリー: ch01.政治, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 1 月 7 日 日曜日
地殻変動はすごい・・・一部の漁港では海水が入らないほどの隆起が認められるそうだ。輪島市の皆月湾や名舟町などで、海岸線が沖に向かって大きく前進したのが確認できるらしい。皆月湾周辺では海岸線が沖に約200メートル進んだ場所があり総延長では約85キロにわたる前進とか。聞いてもよく理解できないでいる。日本地理学会のグループの調査では陸地の面積は計2・4平方キロほど増えたとか。能登半島の沿岸全体で約4・4平方キロの陸化・・・それにしてもますます寒くなる能登半島。早い対策と復興の為に自分が出来る事を。
カテゴリー: ch01.政治, ch10.生活, ch11.経済, 社会問題 | コメントはまだありません »
2024 年 1 月 2 日 火曜日
令和6年の幕開けは・・・
1月2日の午後6時前です。羽田空港で、新千歳空港から向かっていた日本航空516便が着陸した直後に火を吹いている・・・海上保安庁の航空機と衝突したとニュースです。え?全く信じられない事故です。航空機の乗員含め、どうなってしまうのだ・・・と思っている時、乗客の安否のニュースが流れました。海上保安庁の機体に乗っていた6人の方のうち5人の死亡が確認。業務上過失致死とかいっていますが、何かがおかしいと思える。
カテゴリー: 社会問題 | コメントはまだありません »