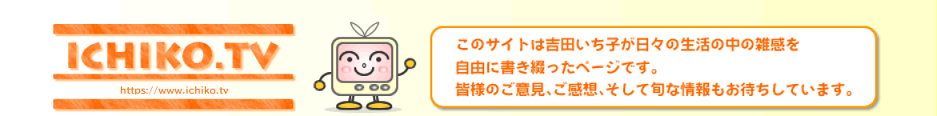今どきの子どもたちは「公衆電話」を知らず、そして「かけられない」という番組を見て、なーるほと!そんな時代なんだと思った。まず電話ボックスにどうしたら入れるのか?もまごつき、10円玉を受話器を外さずかけてみている。10円玉がコロンと落ちてきて「かけられなーい」と言っている姿。あああ、こんな時代かと思った。
もう生活の中では身近なものではないのだ・・・と思いつつ、2011年3月11日の東日本大震災の時の駅の様子がうかぶ。街中の人々は必死に公衆電話の前に並び、必死だった光景だ。スマホも何もかも通じなかったあの日。都心の交通は麻痺し、メールも何も無理だった。公衆電話に人々は群がっていた。公衆電話の少なさに嘆きも聞いた。電話番号がスマホに入っている人は番号の検束も出来ず右往左往していた。どうしようもない脆弱さを見た。
そのうち、ツイッターの呟きを信じた人たちが騒ぎ出したのだが、私はどうも信用出来ず何とか、パソコン通信は出来ないものかと。原稿締め切りに間に合ったものの先方だって右往左往しているに違いないと思った。本当に手も足も出ないという時に、手帳にメモしてあって公衆電話を使える人がどんなに優位だったか、目の当たりにした。
公衆電話・・・そしてダイヤル電話、プッシュ電話もあった。端境期というのだろうか、全く知らずその「時代」を生きていくしかないのだと思った。
ふっと・・・スマホもない時代が思い出された。歌謡曲はそんな「時代」を如実に語る。
松山恵子の『お別れ公衆電話』は「♪汽車に乗ろうと 思ったものを駅の喫茶の公衆電話 いつかかけていた」と切ない女ごころを歌い、小山明子の『恋に落ちて』では 公衆電話ではなく自宅の固定電話だろう。「♪ダイヤル回して 手を止めたI’m just a woman Fall in love」と歌う。切ない女心には「公衆電話」は必須アイテムだったのだ。今なお、スマホの中でその女心は現役であると思うが・・・
公衆電話や自宅固定電話ではないが、コミュニケーションツールの一つとして野口五郎の『私鉄沿線』では「♪伝言板に君のこと 僕は書いて帰ります」とある。当時、駅には伝言板というものがあって、そこに「先に行く」「1時間待った」というような短いMESSAGEが書かれたものだ。時折、その内容の面白さに暫く立ち止まって読んでいたこともあった。心情を吐露するものもあった。
しかし、今どきの若者にはこのような世界は「古典文学」なんだろうなと思うと何か笑いがこみ上げてきた。いずれは、スマホを中心として、ラインだなんだかんだも「古典文学」の世界になるのだろうかって。
ただ、〝以心伝心〟は、太古から未来まで永遠かなと思う今日この頃である。
 1年に一回は集まるメンバーがいる。産経時代の仲間たちである、別に同期ということでなく、もう先輩も後輩もということがなくなった仲間たちである。
1年に一回は集まるメンバーがいる。産経時代の仲間たちである、別に同期ということでなく、もう先輩も後輩もということがなくなった仲間たちである。