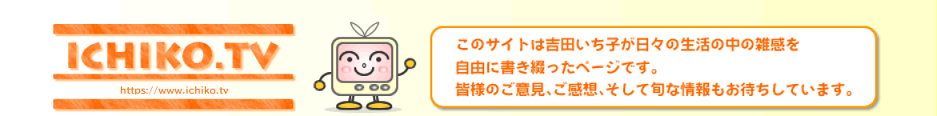今月は誕生月ということもあって?お誕生会とやらの企画を友人たちがして下さる。本日は青山の「アクアビット」で。大好きなワインを飲みながら優雅なランチタイム。デザートに感激。いくつになっても嬉しいものです。10年間日記をプレゼントされた。今日から書こう!みなさま、有難うございます!
今月は誕生月ということもあって?お誕生会とやらの企画を友人たちがして下さる。本日は青山の「アクアビット」で。大好きなワインを飲みながら優雅なランチタイム。デザートに感激。いくつになっても嬉しいものです。10年間日記をプレゼントされた。今日から書こう!みなさま、有難うございます!
‘ichiko’ カテゴリーのアーカイブ
いくつになっても嬉しい!
2014 年 6 月 4 日 水曜日じゃあ、また!
2014 年 4 月 20 日 日曜日毎年、誕生日を迎えると人はひとつとしをかさねる。元気溌剌でも病んでいても、どんな状態であっても、命があればとしをかさねる。
社会にでてから、本当に親しくなった友人が40代のはじめで亡くなった時は、「ああ、人には寿命というものがあるの」かとつくづく思った。思い出が去来するとはこういうことかと思った。出張が多い彼女が、久しぶりに時間がとれた日。銀座で少し長めのランチをとった日。交差点で「じゃ。またね」と何も不思議に思わず、別れた翌日に訃報に接したのだった。こんなことが・・・人生にはあったのだ。翌日に。
もう東京は青葉が眩しい季節へと変わっていく。でも東北に戻った友は「そろそろこれからが見ごろ」と桜を絶賛している。そんな友も集合して、今週末に、サラリーマン時代の友人の偲ぶ会をする予定だ。本の出版記念のお祝いも含めて、日本各地から心をひとつにした友が集まる。4月30日が彼の命日である。例会のあとに東京駅で別れた時も「じゃあ、また」と言っていた。言い方がおかしいと思うが、「何か」が起こって初めてその人の大切さ、過ごしてきた時間の愛おしさが分かるものだ。その時に、決して永遠ということがないことが分かるものだ。
何度か不思議体験をした、そんな気持ちを詠んでみる。
命日に友の化身か紋白蝶
小林カツ代さん お別れの会
2014 年 3 月 31 日 月曜日2014年3月31日(月)。帝国ホテル富士の間で『小林カツ代さんお別れの会』があった。祭壇というよりステージには満開の桜の中で笑っているかっちゃんの写真。献花をする。会場内には多くの書籍たち。そして愛用のキッチン道具も展示されていた。若かりし頃のかっちゃんの写真も多数展示。ただただ懐かしい。神楽坂女声合唱団はかっちゃんが心をこめて作詞した団「緑の星に」を歌う。元団員との懐かしい再会もあった会場。こんな日はくるのか?と考えたこともないことが人生にはある。いつも前向きでケタケタ笑っているかっちゃんにしんみりした気持ちは大敵と思って、みんなでワイワイとね。
「あっという間につくった料理はおいしい!なぜなら「気合い」が入っているから。」 小林カツ代
忘れませんね。いろいろなことを。駅の階段をハアハア登りながら「私、考えついたのよ、今」と編集中の書籍タイトルを言っていたあの日。「階段、登りきった時でいいって~」と言ってもハアハアとのぼりながら何度も言うかっちゃん。楽しかったね!可笑しかったね!
フライパンひとつあればどんな料理だってできる!と当時の私には信じられない魔法を教えてくれたかっちゃん。
「あんた、料理人になるわけじゃないんでしょ?ばかねぇ~それなら使いなさいよ」と野菜の皮むき器を勧めてくれた。どんなに料理がはかどったことよ。
次々と思い出されることを大切にしていこう。
忘れずにしていこう。
捨てられないものたち
2014 年 3 月 26 日 水曜日以前、「断捨離」という言葉が流行した。その時には、それほど感じなかったのだが、モノを「捨てる」という行動・行為が実に難しい。何でも一応とっておくと妙な安心感があるものだ。それは「いつか使う」「いつか役に立つ」という感覚からか?特に、膨大なファイルの山に「フホォー」と大きなため息が出てしまう。こうしたことは気力のある時にしかできないものである。
ファイルの背表紙には「原稿資料」とあった一冊がデスクの奥の奥にあったものだ。また「何かに役立つだろう」ととっておいたものだろう。だいたい、原稿や、ゲラなどはその出版物がでて、たいがいは破棄する。最近は殆どがパソコンでの仕事。フォルダにとりあえずは分類をする。紙の資料は地域別、時代別などカテゴリー別に分類はするものの、ほいさっ~とデスクの上に置いて、時間が経つと紙袋に入れてしまう資料がある。これは?それにも漏れたものだろうか?思い切ってそしてファイルを開けてみる・・・「ああ・・・」と声が出る。いろいろな方の直筆原稿。パソコンの文字うちではない手書きの原稿。中には、原稿用紙に整然と書かれたものもある。その中にかっちゃんこと小林カツ代さんのゲラ直しのコピーが2枚あった。何年前のものだろうか?そうそう、あの時だ!と思いながら、そのゲラの赤字校正を見る。いや、読んでいた。元気いっぱいのかっちゃんの手書きの赤字校正。懐かしいやら・・・言葉が見つからない。来週あたまにかっちゃんの「お別れ会」がある。その前に出てきた原稿直しのコピー。心の中で何かが弾けた。
臨死体験
2014 年 3 月 23 日 日曜日以前、作家の立花隆さんが「臨死体験」という本を出版して話題になったことがある。私の友人の児童文学を主に書いている作家のTさんがなんでも、児童向けに分かりやすい臨死体験の本を書くということで先般、「臨死体験をした人を知らないか?」と問い合わせがあった。いつも親しくさせていただいている陰陽五行の伊勢瑞祥先生が、その体験があるということを話したところ、是非とも会ってみたいということになった。
「臨死体験といえるのかなぁ?」と伊勢先生は言いながらも、取材の日、かなりノリにノッて?、本当に引き込まれるお話しをされた。もう本当に前に何度か、チラッと聞いたことがあって、そのままぼんやりと覚えていたことだが、改めてその体験話を聞くと不可思議極まりなく、人間ってなんだ?とそんなことまで考えてしまっていた。
取材後に、「ああ、思い出した。不思議な夢の話」と言うと、Tさんは「夢でもいいから聴かせてよ」と言った。忘れていた泉が湧き出るように、なんとまあ!不思議な夢の話があるのだろうかと自分でも思った。臨死体験はしたことはないが、自分ではしっかり意識があるのに不思議体験も何度も経験している。Tさんと別れた後、いろいろ思い出して書いていくうちにどうしちゃったの?というほど思い出した。ただもそれだけの話ではあるが、自分も本当の「死」の前に何を見て何を感じるのか?興味は湧いてきた。
授賞式にでてまいりました・・・
2014 年 3 月 17 日 月曜日3月17日は夕刻からサントリーホールで「エンディングメッセージ」の授賞式に出席する。大切な人へのエンディングメッセージということで応募した。人生には「まさか!」があるものだとつくづく。応募したメッセージもいつもいつも思っていることをいわゆる「つぶやいた」感じのものだ。日頃から文章については気負うことが少なくない。つぶやき・・・あまり文章には書かないな。多分、そんな自然体が審査員の方々(萬田久子さん、天野伊佐子さん、クミコ、残間里江子さん)に伝わったのかも知れないな。トークとミニライブもなかなか楽しかった!授賞式後にインタビューを受ける。いつもは「する側」であるがこの夜は「される側」。終活について結構聞かれたが・・・いきなり話をまとめるというのも難しいものがある。話しながら只管、見出しなど考えてしまうものは確実に職業病である。
大切な人へのエンディングメッセージ
2014 年 3 月 12 日 水曜日歌手のクミコの新曲のコラボ企画として「大切な人へのエンディングメッセージ」に応募した。私が光になる前に愛するあなたに遺したい。大切な人へのエンディングメッセージということだった。「吉田さん、一時審査に入りました」と連絡をいただいたのがつい先日。まあ、久しぶりにすごいね~程度に思っていたら、なんと、昨夜「最終審査にはいりました。入賞おめでとうございます。」との連絡。人生には本当にまさか!があるものだね。3月17日に授賞式およびトーク&ミニライブが東京・赤坂のサントリーホール 小ホールで行われる。審査員は女優・萬田久子、天野伊佐子さん(故・天野祐吉さん夫人)、残間里江子さん。たまたまというか、いつもいつも心の底から思っていることをまとめて書いたもの。いわば等身大の気持ちそのものである。ある記事には “遺言歌”を起点に広がりを見せそうな「エンディングメッセージ」。このムードが高まれば、クミコの4年ぶりの紅白の舞台も見えてくるのかもしれない・・・とあった。自分も、エンディングを意識し始める「お年頃」そのものになったということであろうな。
ご縁
2014 年 3 月 4 日 火曜日先般、発行した友人の遺稿作品「幻の稲荷山王朝 ワカタケル大王と埼玉古墳群の謎」。3月3日に“ひなまつりの日に”ということで、故人の弟さんからメールが届いた。親戚一同全てに配り終えたとのこと。我々メンバーの話も昔、聞いたことがあった・・・そんな件も書かれてあった。弟さんの言葉のひとつひとつに何とも言えぬ亡きお兄さんへの想いが伝わる。人と人とのご縁とは本当に一期一会というのだろうか?社会生活のひとこまで出会って、今、こうして友の遺稿作品をまとめたということ。これは、自分の人生のひとこまでもあろうなと。今は亡き友に対して、いろいろ有難う!と心から言いたい。
きっと桜の華やぐ季節には・・・
2014 年 2 月 24 日 月曜日朝一で友人の遺稿作品集が納品された。東日本大震災のあった年の4月30日。末期癌の告知を受けながらも、積極的にホスピスに入ることを願った友人。奥さんや兄弟など家族の心配をしながら・・・無念だったと思う。
彼が長年、あたためてきたテーマだった稲荷山王朝の研究。プロローグを読めば、その研究への意気込みが伝わる。しかし、エピローグには、彼の遺された「時間」の無さ、寡黙な中に静かな叫びさえ感じ取ることが出来る。
遺稿作品「幻の稲荷山王朝 ワカタケル大王と埼玉古墳群の謎」。手にとれば、その重みに彼の気持ちの重ささえ伝わる。メンバーで出版を思い立った時には、もう少し早くに出版出来ると思っていたが・・・しかし、今は違う。この時間が残された私たちにも必要だったということが分かるのだ。私たちメンバーが日常生活を過ごしながら、そんな中で彼への想いを一つの形に仕上げていく、そんな凝縮した時間。これが、きっと天国にいる彼への一歩メッセージが届きやすい「時空」へと入っていったのではないかと思っている。
「学会とは真逆理論だね」といういろいろな人々の感想や評価に戸惑うこともあったが、あるかたい信念と意思というのだろうか。要は友情であろう。且つ、考古学者の田所真先生の「真逆理論」は分かっていらっしゃる中でも「書籍化を勧める」という言葉に私たちは想いを一つに出来たのだ。
天国でも推敲しているのだろう。ニヤニヤと笑っているのだろうか?好きなワインでも飲みながら?。桜のはなやぐ季節も間近である。友は再び、集まり、この作品を読みながら、貴方の話をするだろう。人生のたまたま・・・産経新聞社という組織の中で、たまたま、第4期の中堅社員研修の中で知り合って。たまたま同じテーマに関心があり研究を始めた仲間。偶然ではなく、それはよく言われる「必然」の出会いと出来事だったのかも知れないね?そう思うよ。メンバーが再会する日、忘れていた涙も零れるかも知れないね。
ほころぶ梅の花に笑顔
2014 年 2 月 21 日 金曜日季節とは本当に素晴らしい。教えたわけでもないのに?梅の花が咲き始めた。本当にほろっほろっという感じである。寒くても春が着実にやってくることが分かる。